インタビュー・文章 尾上そら
――留学から帰国後、初のOrganWorks公演ですが、スペインの余韻はまだ残っていますか?
向こうでの日常があまりに濃すぎたせいか、もはや懐かしいというか、かなり前のことのように感じています。
不思議ですね。もちろんカルメン・ワーナーと率いるカンパニーとは、留学以前から交流があり、よく知っていたはずなんですが、彼女たちの言葉や文化、生活のなかに単身飛び込んだからこそ知り、感じられたことも多くて。
たとえば長い休暇や日々のシェスタ(食事や昼寝も含むしっかりとした昼休み)など、マイペース極まりないことで知られるスペインのライフスタイル、それらがキリスト教のカトリックの教えに基づいていることや、日常の中に歴史が色濃く残っていることなど、新鮮で刺激的な体験をさせてもらいました。
不思議ですね。もちろんカルメン・ワーナーと率いるカンパニーとは、留学以前から交流があり、よく知っていたはずなんですが、彼女たちの言葉や文化、生活のなかに単身飛び込んだからこそ知り、感じられたことも多くて。
たとえば長い休暇や日々のシェスタ(食事や昼寝も含むしっかりとした昼休み)など、マイペース極まりないことで知られるスペインのライフスタイル、それらがキリスト教のカトリックの教えに基づいていることや、日常の中に歴史が色濃く残っていることなど、新鮮で刺激的な体験をさせてもらいました。
――そういった経験も『机の器の机』には反映されているのでしょうか
『机の器の机』は「あうるすぽっとシェイクスピア・フェスティバル2014」への参加作品ですが、イングランドに生まれたウィリアム・シェイクスピアという、世界中に知らぬ人のいない劇作家とその作品を考えるうえで、意外にもスペインという国の存在がヒントになったんです。
僕が最初に関心を持ち、切り口としたのはシェイクスピアの活動した時期のイングランドの社会情勢と、そこに大きく影響を及ぼす宗教の存在でした。シェイクスピアが活躍した少し前、16世紀の初頭からイングランドは初代のエリザベス女王の統治下にあり、それまで続いた王位継承を巡る多くの血を流す争いに、終止符を打って間もない頃です。王や女王が変わるたびに国の宗教も変わっており、エリザベスがプロテスタントの信者だったことに対し、その前の女王・メアリー一世は熱烈なカトリックの信者でプロテスタント信者の命を奪うほどに激しく弾圧。さらにはカトリックの大国スペインの皇太子と結婚もしており、イギリスとスペインが戦争するきっかけにもなっているんです。
僕が最初に関心を持ち、切り口としたのはシェイクスピアの活動した時期のイングランドの社会情勢と、そこに大きく影響を及ぼす宗教の存在でした。シェイクスピアが活躍した少し前、16世紀の初頭からイングランドは初代のエリザベス女王の統治下にあり、それまで続いた王位継承を巡る多くの血を流す争いに、終止符を打って間もない頃です。王や女王が変わるたびに国の宗教も変わっており、エリザベスがプロテスタントの信者だったことに対し、その前の女王・メアリー一世は熱烈なカトリックの信者でプロテスタント信者の命を奪うほどに激しく弾圧。さらにはカトリックの大国スペインの皇太子と結婚もしており、イギリスとスペインが戦争するきっかけにもなっているんです。
――その後の世界情勢の中で、イギリスとスペインの国力が逆転しているのは皮肉ですね。
本当にそう思います。カルメンたちスペイン人は、生活に根ざしたカトリックの教えが現代にそぐわないことを自身でよく笑い飛ばしたりしていましたが、それも信仰が日常の中に深く浸透しているからこそだと僕には思えた。自分が生きている遥か昔から続くもの、その影響下に生きる人々の姿は、400年以上前から現在まで、その地位も人気も衰えることなく上演し続けられるシェイクスピアの存在と創作を考える手がかりになったんです。
それに、以前から好きだったキリスト教の聖人や宗教家を描いた宗教画も、スペイン滞在中に現地の美術館で色々見ましたが、それらの絵画も創作に大いに刺激を与えてくれました。エル・グレコらが描く宗教画には信徒に向けた「サイン」(ポーズや使う色に宗教上の意味が込められている)がある。そんな「絵が言葉を生み出す」ことが、僕には非常にそそられることで。宗教画に絵が描かれた一場面、その続きを舞台上で表現してみるようなことや、絵の中の光のあり方を照明の発想に取り入れてみるとか、それら絵画の衣裳のイメージ、より多く着て「身体を隠し」たり、カラフルな色彩を取り込んでみるなど、色々と考えているところです。
もともと「OrganWorks」の創作は、普段以上に衣裳や音楽、照明など他のプランナーとの意識的な作業がウェイトの大きなもの。その創り方の利点を、大いに活かした創作に今回もなっています。
僕にないものを補い、イメージを形にする「間」をプランナーが埋めてくれる。それが「OrganWorks」の大きな強みですから。
それに、以前から好きだったキリスト教の聖人や宗教家を描いた宗教画も、スペイン滞在中に現地の美術館で色々見ましたが、それらの絵画も創作に大いに刺激を与えてくれました。エル・グレコらが描く宗教画には信徒に向けた「サイン」(ポーズや使う色に宗教上の意味が込められている)がある。そんな「絵が言葉を生み出す」ことが、僕には非常にそそられることで。宗教画に絵が描かれた一場面、その続きを舞台上で表現してみるようなことや、絵の中の光のあり方を照明の発想に取り入れてみるとか、それら絵画の衣裳のイメージ、より多く着て「身体を隠し」たり、カラフルな色彩を取り込んでみるなど、色々と考えているところです。
もともと「OrganWorks」の創作は、普段以上に衣裳や音楽、照明など他のプランナーとの意識的な作業がウェイトの大きなもの。その創り方の利点を、大いに活かした創作に今回もなっています。
僕にないものを補い、イメージを形にする「間」をプランナーが埋めてくれる。それが「OrganWorks」の大きな強みですから。
――平原さんは他にもソロ作品を創作する「ノーコン」や「瞬project」「C/Ompany」、もちろん「コンドルズ」もですが、とても多くのカンパニーやユニットに参加していらっしゃいますよね。
確かに。自分主導の「OrganWorks」と「ノーコン」に関して言えば、前者は実験と挑戦の場で、後者は完成度を高めるため突き詰めた創作をする場、でしょうか。「瞬project」は他とはちょっと違うカンパニーというか……一番最初、北海道で出会った仲間たちとつくったもので、カンパニーなどよりもっと流動的な、“スタイル”のようなものだと思っているんです。他は集まって作品をつくることが目的ですが、「瞬project」は集まることで何かが起きる、創作以前に刺激しあえる対等な立ち位置にいる仲間というか。でも実際の創作になると先導者が必要で、バランスも変わってくる。そこが難しいところですが、僕という人間の原点、ダンサーとしてのベースがあるのが「瞬project」です。11月にはずっと「瞬project」で一緒にやってきた東海林靖志と12、3年ぶりにデュオを踊ることになっているんですが、それは非常に楽しみです。
――「C/Ompany」は大植真太郎さん主導のユニットですよね。
ええ、「C/Ompany」は7割大植が仕切り、残り3割他の人間が知恵を絞るというやり方です。大植はスウェーデンを拠点にするダンサー、振付家で僕にとっては非常に面白い存在。ノイマイヤーやキリアンなど一流のカンパニーに所属していたキャリアがあり、世界屈指の身体とテクニックを持っているにも関わらず、気ままにフリーランスで踊っている。良くも悪くもチャランポランというか、まぁアーティストにはそういう人が多いけれどノマド(遊牧民)な感じで(笑)。でも創作の上では、僕を良い意味で否定してくれる存在なんです。自分のつくるものが容易には通らないけれど、そのことが納得できる。逆に自分の考え方、発想の癖がどういうものかに気づかされる。そういうところがコンドルズとは大きく違うんです。筋道はないけれど、「こういうことをしたほうが正しいよね」という暗黙の了解がお互いにあって、だからこそ非常にクリエイティブな現場になる。すごく大事な場所です。
それぞれの場で、考えるために使う脳の部分が違う感じなんですよ。コンドルズで得たエッセンスを、大植のときに使うとか。
それぞれの場で、考えるために使う脳の部分が違う感じなんですよ。コンドルズで得たエッセンスを、大植のときに使うとか。
――「コンドルズ」は平原さんにとって、どんな場なのですか?
作品に向かっていくとき、「何を考えるべきか」「どういう状態でいるべきか」という前提条件を教えてくれた場所、でしょうか。まったくゼロの、何もない状態から想像し、創造することがどういうことか、その過程に何をすべきかを僕は「コンドルズ」で学んだ。ダンサーの中には振付家の指示を待ち、自分からは動かない人もいる。それはそれで一つのやり方ですが、「コンドルズ」では自分からどんどん提案しないと前に進めない。今回客演してもらう、ぎたろー君もそれは身に染みついているので、現場で起こる停滞に対して自分で考え、「これはどう?」と提案してくれる。創作に前のめりになる、ないなりに最初の線を引こうとする、そういう姿勢は有難いですね。
――それぞれのカンパニーで違う手応えを感じられている。今、とても豊かな環境にいらっしゃるんですね。
すごく幸せだと思います。スペインでお世話になったカルメン・ワーナーのカンパニーも、もう25年の歴史があるんですが、メンバーの多くがカルメンの言葉に対する理解力を持ち、意図の伝達が凄まじいスピードで行われる。まるでカルメンが何人もいるように。「『窓』をモティーフーにインプロ(即興)で作品をつくりましょう」と言えば、1、2時間平気でインプロをやり続け、1週間もすれば作品ができそうなほど、大量のアイデアがメンバーから出て来る。何を探せばいいかを、メンバーが瞬時に理解できるんです。あの集団性には大きな魅力を感じました。創作のために必要なものが全て揃っている感じで。だから、僕も「OrganWorks」を正式に集団化することにした。今の自分が、自分の創作をするための「場」の必要性を、スペイン滞在中に強く意識したからだと思います。
――お話しを伺うほどに、帰国後の所信表明、今後の平原作品の方向性が見えてくる作品になりそうに思えます。
在外研修をひとつの区切りだとすると、その後の一発目の創作が、よりによって演劇のクラシックが題材というのは、自分でもとても面白くて。集団性の大切さを自覚できた後ですし、ストリートダンス、ラップなどにルーツがある僕は、創作の過程で「言葉」を意図的に使ってきましたが、シェイクスピアはまさに「言葉」の化身。「やっぱりこうキタか」と思うところもありますし、自分自身がこの創作の先に何を見出すか、ワクワクしてもいる。
生み出した作家自身が死んでも、言葉は何百年も生き続けて作家を不滅のものとする。そこに挑む僕らの身体はあまりに儚いけれど、言葉を持たない肉体の不安定さを、敢えて強靭な言葉にぶつける、対峙させることで見えて来るものがあるはず。自分にとって、今後もテーマになり続けるであろう「言葉と身体の対峙」について、この作品を通してさらに考察を深められたら、と思っています。
生み出した作家自身が死んでも、言葉は何百年も生き続けて作家を不滅のものとする。そこに挑む僕らの身体はあまりに儚いけれど、言葉を持たない肉体の不安定さを、敢えて強靭な言葉にぶつける、対峙させることで見えて来るものがあるはず。自分にとって、今後もテーマになり続けるであろう「言葉と身体の対峙」について、この作品を通してさらに考察を深められたら、と思っています。
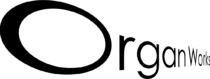
[…] けた内容がパンフレットに掲載されていますが、作品以外のことにも話が発展し掲載しきれなかった内容をサイトで公開することにしました。 こちらのページからお読みいただけます。 […]