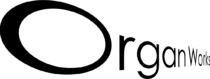■ようやく「共有」の初動が浸透し始めた
――『TSURA』は、今おっしゃったカンパニーづくりの過渡期に生まれた作品なんですね。
平原 そう考えていただいて結構です。ただ、『TSURA』には参加しなかったOrganWorksのメンバー、音楽の熊地勇太が作品を観た時に「全員野球になっていない」と言ってくれた。
彼の言葉には信頼を寄せているので、どうしてそう見えたのかを検証するためにも、カンパニー初のショーケース公演『Out of Repertoire Collection 2015=アレコレ2015 』を企画しました。僕以外のメンバーが振付けた小品と僕のソロなどで構成していますが、「平原慎太郎のOrganWorks」ではなく、メンバーの個々が作品とカンパニーに、一層の自覚と責任を持てるようになるためのステップになれば、と考えた結果です。稽古中の今も、例えば渡辺のシーンなら「ここは渡辺の持ち分だから」とメンバー全員でひたすら見ている。
――随分とプレッシャーのかかる稽古場ですね。そのぶん研ぎ澄まされることも多いのでしょう。
平原 確かに。並行して行っている『TSURA』のツアー用の稽古では、たとえば不在の東海林靖史の代わりを女性ダンサー(高橋真帆)が踊ってみたりもしている。そのことで、メンバー内での役割や存在の「違い」を考えることになればいいなと思っているんです。
――スペイン、マドリードで上演する際も初演と同じメンバーで臨むのでしょうか。
平原 はい、同じダンサーです。
――個人的には実験要素の強い、これまでよりもデコボコの大きな作品だという印象もあります。リ・クリエイションに加えて海外での上演となる今回、集団性を強化していくと共に、作品をどう深化させるのでしょうか。
平原 『TSURA』はシーンを並列するのではなく、「層」として重ねていくという手法を狙いました。
その「層」にはいわゆるまとまりのあるストーリーはありません。
ただ、「裏表の関係性」「見えている表面から、裏側は窺い知れない」などという、テーマのようなものは僕のなかにはあるんです。
初演時は、その「層」の重ね具合がボケていた部分があり、わかりにくい印象があったかも知れませんが、リ・クリエイションに際して個々の「層」がシャープに、より焦点が合った状態で提示できるように心掛てます。結果、伝わりやすくなるのではないかと思っています。
――コミュニケーション・ツールとして表情や仕草、ボディ・ランゲージまでフルに使う欧米の文化圏のほうが、より深く伝わる作品かも知れませんね。
平原 そんな気がします。そのうえでメンバーそれぞれの身体の面白さ、強さがしっかりと伝わるように仕上げていきたいですね。スペインの観客に「身体の強いダンサーだ!」と思わせたい。そこがダンスを観るうえでの真実だと僕は思うんです。
――平原さんはご自身が、作品のシークエンスごとに身体の質感を変えられるような、特別な感性を持っていると個人的に思っているのですが、それをメンバー全員で共有できるとしたら、すごいカンパニーになりますね。
平原 ええ、アレを集団でできると想像しただけで、僕自身もワクワクします。今はまだその段階ではありませんが、それでも、たとえばOrganWorksで「面を変えよう」と言うと、「全身の前の部分を面としてスクエアに動かす」ことになる。さっきの、前川さんとイキウメの劇団員の方たちと同じような言葉の共有が、少しずつですができ始めているんです。身体を細かくパーツに分け、どこをどう動かすかを同じ言葉で共有できれば、創作の速度は飛躍的に上がるはず。そのための初動が、ようやくカンパニー全体に浸透しつつある、というのが現状だと思います。
――その最初の成果が、『TSURA』マドリード公演で問われると。
平原 こんなに「怖い」と思っているのは久々です。僕、人の評価はどうでもいいとか口で言うわりに、実は気にしぃなんですよね(笑)。でもコレ、イヤな怖さではないんです。予兆の前の怖さ。
だから、同時に早くスペインの観客の反応を知りたくもある。納得のいく反応をいただくためにも、ひたすら作品を深めるしかないと思っています。
――帰国後の報告を楽しみにしております。
インタビュアー・文章 尾上そら
スペインの観客に「身体の強いダンサーだ!」と思わせたい
前のページへ・2